忘れられるものー小説、野球、映画の話。
新潮文庫の「村上柴田翻訳堂」という企画は、
「毎月押し寄せる新刊に追われるようにして、古い文庫本が静かにひっそりと退場していきます。そのように姿を消していった作品の中には、「この名作が手に入らないというのは間違っているぞ」と苦情を呈したくなるものもあれば、「個人的にはけっこう好きだったんだけど、やはり生き残れなかったか」と淋しく感じてしまうものもあります。そういういくつかの作品を拾い上げ、もう一度何らかのかたちで新刊として復活させ」よう、
というコンセプトで、2016年から2017年にかけて村上、柴田両氏が選んだ10作品が順次再刊された。こういう企画をさらりと実現させてしまう二人はやっぱり凄いなぁ、とつくづく思う。僕は、サローヤンの『僕の名はアラム』、キングストンの『チャイナ・メン』、ニコルズの『卵を産めない郭公』、フィリップ・ロスの『素晴らしいアメリカ野球』を読んだ。最初の3冊は面白かった。『素晴らしいアメリカ野球』は30年前と同じで最後まで読むことができなかった。長いんだよね。退屈なんだよね。世に云う「不朽の名作」ってのの中にもこの手のやつがある。何度挑戦しても最後まで読めなくてこっちが悪いような気にさせてくれる。『アンナ・カレーニナ』とか『ボヴァリー夫人』とか。『素晴らしいアメリカ野球』もこの度めでたく僕の「いつか最後まで楽しく読めるはず本」のリストに加えられた。
それにしても『素晴らしいアメリカ野球』に出てくる野球選手たちはガラが悪い。思えば、つい最近まで日本野球だって立派にガラが悪かった。今は違いますね。僕は年に何度か家族にせがまれて福岡ドームに野球観戦に出かける。屋根付きの野球場にもドンパチせからしい応援にもなかなか慣れない。情けないプレーを立て続けられると大きな声で野次りたい衝動に駆られるが、暖かい声援以外の大声は禁止されているかのようにシンとして誰も何も云わないから僕も黙らざるを得ない。乱闘もないし、審判の判定に文句を付けた監督が退場になることもない。整然と試合は進んで行き、それでいて試合時間だけはやたらと長い。空調が行き届いて妙に涼しいからバカ高いビールを飲む気にもならない。面白くない。云っちゃあなんだけど女たちが選手を甘やかせ過ぎてるね。優しくし過ぎてるね。まあ、興行としてのプロ野球を立て直せたのは彼女たちの力やけんね。仕方ないですな。ガラの悪い客と選手たちはタバコの煙と一緒にどこか別の場所へ消えてしまってもう帰ってこないんでしょう。淋しかです。ついでに云うと、福岡ドームに数年前から現れたホームランテラス(ラッキーゾーン)も大嫌いです。ホームランがたくさん見られるように、って野球バカにしてません?孫さん、あなた野球も野球選手も本当は嫌いでしょ?附設時代に久留米のピーコックで近所の工業高校のガラの悪い野球部員にカツアゲされたとか?
新しい波に押されて退場していったもの。
映画ならいくつか思いつく。どんなに面白くても残らない作品ってあります。キャストにもスタッフにも誰一人有名な人がいなくて、その後も誰一人として名を成すことができなかった映画なんかはソフトの形態が変わるタイミングで消えて行くみたいです。逆にくだらなくても監督や役者がその後有名になると遡って作品も掬い出される。ショーン・ペンがデビューしたお色気青春コメディ『初体験リッジモント・ハイ』みたいに。
インターネットの普及とともに、市場から淘汰された作品にもまた出会える機会が増えた。タイトルやその他わずかな手がかりさえあれば大抵の作品にはたどり着ける。例えば、『ヘブンリー・キッド』と云う昔テレビで観たB級映画をアマゾンで見つけて取り寄せたが、変わらず面白かった。この映画は当時土曜の昼間なんかに何度もやってたからよほど評判良かったはずだけど、知った顔が一つもなくてね。埋もれちゃいましたね。
同じように掘り出そうとしてどうしても探せなかったものもある。
「クラス・オブなんとか」ってタイトルだった。「なんとか」のところには西暦の年号が入る。このタイトルじゃ検索掛けてもどっかの高校の卒業写真が山のように出てきて二流の忘れられた映画にはたどり着かない。いや、山というより海だな。古代生物を探して深海を探索するような途方もなさを感じましたね。ああ、こりゃダメだ、と。
ちなみに「クラスオブなんとか」とはこんな話である。
舞台はアメリカの田舎町。町はエグゼクティブ・クラスとワーキング・クラスにはっきりと分かれている。住むエリアが違い、高校もそれぞれある。対立していると云うほどではないが、お互いを良く思ってないから交わることはない。主人公は山手側の高校生で、ロックンロールとダンスに夢中な男の子である。ロックンロールとダンスに夢中であることは彼の住む山手の高校生としてはちょっと変わってる。60年代初頭のエグゼクティブ・クラスの高校生はロックンロール(我々が云うところのオールディーズ)を聴かない。らしい。ロックンロールとダンスは不良のもの、ワーキング・クラスのものである。
ところで、下町にはテレビ局があって、そのテレビ局で若者に大人気の看板番組「ボブのダンス・バトル」(タイトル適当)は、カリスマ司会者ボブのリードの元に町の若者が毎週ダンス・バトルを繰り広げる。若者は前回のチャンピオンに挑戦し、あるいはそれを負かし、あるいはチャンピオンが防衛する。ある日主人公はその番組のオーディションに出かけて行くんだけど、山手の高校生であることで会場に集まった連中に嬲られて散々な目に合う。しかしそこでひとりの女の子と出会う。仲良くなってお互いの家に夕食に呼ばれたりする。主人公の山手の家に女の子が行った時のことだ。隣に住む幼馴染の女の子がやってきて話に入ってくる。下町からやってきた女の子は自分の夢を語る。自分はウエストサイドストーリーのナタリー・ウッドみたいなミュージカルスターになるのだ、と云う。すると幼馴染は「あんたバカねえ、ナタリー・ウッドは唄なんか歌えないのよ。あの映画は吹き替えなんだから」なんて云って女の子を地味に虐めるのである。「やめろよ」と主人公が云ってもツンとしてまるで聞かない。そんなことがあっても二人は仲良く付き合っていた。
そこに女の子の元カレがハーレーに乗って現れる。グリースのジョン・トラボルタみたいな奴だ。「なんだお前は?こいつは俺の女だ」「何よ今更。もうあんたの女なんかじゃないわ。わたしのことなんてズ~とほっぽらかしじゃないの」みたいなやりとりがあって、やがて主人公とハーレー男は勝負することになる。ケンカでもチキンレースでもなくなぜかダンスで。どこかの倉庫かなんかで。嵐の夜に一晩中踊り明かして、彼らはお互いを解り合う。「この町は俺には小さ過ぎる。俺はハリウッドに行こうと思ってる。スターになるんだ。自分を試すんだ。俺はバカなんだ。こんな生き方しかできないんだ。あいつも連れて行く。あいつがいないと俺はダメなんだ」そうハーレー男は主人公に打ち明ける。主人公の心は揺れる。なぜなら彼女の心もハーレー男にあることを知っているから。問題は彼女の親だ。彼らは主人公を気に入っている。ハーレー男は彼らにとっては可愛い娘の人生を台無しにする毒蛇のような存在だ。男を撃ち殺しても娘を渡さないだろう。
話は変わって、「ボブのダンス・バトル」の打切りが決まった。視聴率が低迷しているのと、それに伴って元々ロックンロールもダンスも嫌いだったスポンサーが別のプログラムを望んでいると云うのが理由である。自分の力に絶対の自信があるボブには納得がいかなかったが、時代は確かに変わりつつあった。ベトナム戦争が泥沼化し始めていた。彼らの小さな町からも若者たちが徴兵されてポツりポツりといなくなっていた。主に下町のワーキングクラスの若者たちが。それまでのロックンロールはもう新しい時代を表現できなかった。最後の日、泥酔状態のボブはバディー・ホリーをバックに若者たちと共に踊り狂って番組を終える。苦情の電話が鳴り止まないがボブは気にしない。
ハーレー男と彼女の駈落ちの日。主人公は町外れまで彼らを見送りに出かける。家の車は家族が使っていたので車庫にない。主人公が途方に暮れていると隣の幼馴染がパパの車を使いなさい、とキーをくれる。彼女もなかなかいい娘なのだ。幼馴染のパパ自慢の新車を飛ばして主人公は二人に別れを云いに行く。三人が別れを惜しんでいるその時、彼女の父親が車で迫ってくるのが見えた。ヤバイ。急いで、と云って主人公は二人をハーレーに急き立てる。ハーレーが土煙を上げて走り出す。お父さんの車が迫る。主人公は自分の乗ってきたシボレーを体当たりさせてそれを止めた。二人を乗せたハーレーは踏切の向こうに走り去り、すぐにやってきた貨物列車に遮られて見えなくなる。
翌日、たぶん大人たちに散々搾られたであろう主人公は自分の部屋のベッドで頭を抱えている。そこへ隣の幼馴染の女の子が一枚のレコードを持って入ってくる。
「ねぇ、これ一緒に聴こうよ」
「ああ、そんな気分じゃないよ。ウエストサイド物語なんか聴きたくないよ」
「違うのよ。ウエストサイド物語じゃないのよ。何て云うか、こう、すっごく新しいの。今まで聴いたことないくらい」
彼女が主人公に構わず勝手にターンテーブルにそのレコードを載せて針を落とすと、スネアの「タンッ」という音がしてボブ・ディランの「Like A Rolling Stone」が流れてくる。主人公は「オッ!?」と云う顔をして起き上がって彼女のそばにきて云う。
「ちょっとそれ見せて」
主人公は「Highway 61 Revisited」のレコードジャケットを手に取る。
終わり。



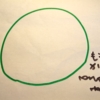
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません